「ハスラー」 1961年 アメリカ
監督;ロバート・ロッセン
出演;ポール・ニューマン,ジャッキー・グリーソン、パイパー・ローリー
2009年9月25日 NHKBS録画 自宅ごろ寝シアター
 若きハスラー、エディ。彼は伝説のミネソタ・ファッツ(ミネソタの太っちょ)に大勝負を挑むも、精神力の弱さで惨敗。傷つき、金も失ったエディはサラという女子大生と出会う。エディは再びファッツに挑むために、賭博元締めのバートと組むことに…。
若きハスラー、エディ。彼は伝説のミネソタ・ファッツ(ミネソタの太っちょ)に大勝負を挑むも、精神力の弱さで惨敗。傷つき、金も失ったエディはサラという女子大生と出会う。エディは再びファッツに挑むために、賭博元締めのバートと組むことに…。
DVDのジャケ写真はカラーだが映画はモノクロ。ハスラーとは、ギャンブルで詐欺まがいのことをして相手から大金をせしめる者のこと。日本では単にビリヤードする人のことだが…。勝負師にとっては勝ち負けが全て。エディは腕だけならファッツより上かもしれない。でも勝てば調子にのって墓穴掘るし、負ければ言い訳ばかりする。負けたのは「人間が劣る」からだ。「俺は負け犬か?」とほざいてるばかりいるエディに、サラは勝ち負けよりもっと大切なものがあることを分かって欲しかったのだと思う。勝負師が破天荒で、女(家庭)を犠牲にするというのはよくあるパターンだが、本作はそこを非常に真面目に、人間として何が大切なのかを掘り下げて描いている。そのため、ビリヤードシーンが大半を占めるにも関わらず、勝負しか目になかった若者が、勝負以外のところで人生の挫折を味わいながら成長していく姿が強く印象に残る。サラを失ってはじめて彼女の愛に気づいて、悲しみ苦しみ、勝負師として欠けていた精神的強さを得るというのは、人生の皮肉…。ちょっと引っかかったのは、なぜ、サラが賭博元締めのバートに体をゆるしたかである。無理矢理ではなく、自ら。絶望して自暴自棄になっていたんだろうけど、エディが身を落とそうとしている世界はこんなにも薄汚いと、言葉で言っても分からない彼に、最後の最後に教えたかったのかな。
賭博元締めのバートのセリフが印象的。極悪人だけど、勝負を情けなしに見てきた彼が言うことは現実的で、いちいち当を得ている。勝つことは重荷で、負けることは簡単。だから勝てない人間はさっさと重荷を下ろして、負けた時の理由を探し、後悔に浸るのを楽しむ。自分から敗北の道を選んだ、とかね。触れらたくない、自分にも言い訳して誤魔化している弱みを目の前に引っ張り出す。多分、エディのようなプライドの高い人間の闘争心を引き出すには、こういうぐぅの音もでない言い方が一番効果があって、人間操作術としても何か現実味があるなぁと。バートのセリフに凹むのはきっとエディだけじゃないはず(←相当凹んだ人>_<)。
実は、ポール・ニューマンの若い頃の作品ははじめて。もう少し後の『明日に向かって撃て』、『スティング』などの成熟した演技に比べると、まだ肩に力が入っているけど、青臭いしょうもないハスラーから大人の男へと雰囲気がガラッと変わっていくところはさすが。ファッツ役のグリーソンも、大物らしい落ち着きはらったたたずまいに見惚れてしまう。ビリヤードシーンは、ほとんどが本人によるもの。グリーソンはもともとプロ級の腕前だったが、ポールの方はこの役のために猛特訓したそう。ちなみにミネソタ・ファッツは実在の人物。
DVDのジャケ写真をカラーにしたのは間違い(売上げ増加ねらったのかもしんないけど)。この時代、ハリウッドではカラーが主流になりはじめていたから、監督は敢えてモノクロを使ったのだ。勝負、ジャズ、タバコの煙、酒、そしてビリヤード。モノクロの方が絶対クール。この写真は、作品のイメージとまったくかけ離れている。
「キャンディ」 1968年 アメリカ=イタリア=フランス
監督;クリスチャン・マルカン
出演;エヴァ・オーリン,リンゴ・スター,ジェームス・コバーン,マーロン・ブランド,シャルル・アズナブール他
2009年月日 DVD 自宅ごろ寝シアター
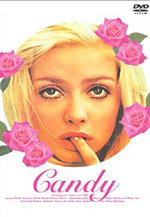 純粋無垢(無知?)であどけない女子高生キャンディが、次々と変な男にせまられてしまう。ただそれだけの話。
純粋無垢(無知?)であどけない女子高生キャンディが、次々と変な男にせまられてしまう。ただそれだけの話。
支離滅裂。メキシコ人庭師(リンゴ)が馬鹿っぽかったり、人を助けるべき医者(コバーン)や軍人(ウォルター・マッソー)が狂っていたり、背むし男(シャルル)が体のせいでエッチしてくれないのかと怒ったり、宗教家(マーロン)は偽物で言うことなす事嘘だらけだったり。原作がテリー・サザーン(『イージー・ライダー』『博士の異常な愛情』の脚本家)だし、風刺や社会批判があることは分かるんだけど、支離滅裂すぎてピンとこない。
はっきり言って、中味はない。エヴァ・オーリンの可愛さと健康的なセクシーさ、そうそうたる大俳優たちが馬鹿な役で怪演を披露している。それが楽しめれば、おk。
60年代の性の開放、サイケデリック、伝統的価値観を拒否する若者文化の盛り上がりを反映してるのは分かるけど、若くないお姉さんから見ると、そうした作風とは裏腹に、キャンディが普遍的な男の妄想の産物にしか見えないの。最近の秋葉原あたりのアニメフィギュアと大して変わんない。かわいくて、おっぱいがはち切れそうな女の子が、どんな男だろうと、疑問も持たず、大して抵抗もせずに体を惜しみなく許していく。でも、スレたりもせず、永遠に天然で、かわいらしい。そして、エンディング。真っ白なドレスのキャンディが、今まで出会った男たち前を通り過ぎると、花で飾られ、どんどん美しくなっていく。女性は男に与えるほど美しくなるという意味なのか?。キャンディは男にだまくらかされてばかりで、男の欲望に対しては徹底して受け身で、学習能力もないわけだけど、それが女の美しさだとばかりに肯定しているようにも取れる。キャンディという女性像は時代の先端を行ってるような衣をまとってるけど、内実は何の新しさもないのよね。
「未来惑星ザルドス」 1974年 イギリス
監督;ジョン・ブアマン
出演;ショーン・コネリー,シャーロット・ランプリング
2009年9月3日 DVD 自宅ごろ寝シアター
 核戦争で荒廃した未来社会。一部のエリートたちは不老不死となり、ボルテックスという理想郷で暮らしていた。他の人間は獣人と呼ばれ、ボルテックスとは完璧に遮断された荒廃した土地で野蛮な生活を送っており、ボルテックスを神とあがめていた。獣人の世界では、人口をコントロールするためにボルテックスによって選ばれし殺人隊がいたが、殺人隊のゼッドが神の秘密を探ろうとボルテックスへ侵入する。
核戦争で荒廃した未来社会。一部のエリートたちは不老不死となり、ボルテックスという理想郷で暮らしていた。他の人間は獣人と呼ばれ、ボルテックスとは完璧に遮断された荒廃した土地で野蛮な生活を送っており、ボルテックスを神とあがめていた。獣人の世界では、人口をコントロールするためにボルテックスによって選ばれし殺人隊がいたが、殺人隊のゼッドが神の秘密を探ろうとボルテックスへ侵入する。
低予算で製作された、知る人ぞ知るカルト的人気のSF映画。冒頭からいきなり手作り感ある顔面岩がふわふわ飛んできて、赤褌一丁で胸毛全開のショーン・コネリーがっ!。このカルト臭、たまんないなぁもう(笑)。
監督のジョン・ブアマンが脚本も担当。アイディアは壮大で面白いが、脚本の完成度が低い。前半はだらだらしてるに、後半に入ると一気に謎明かしされる。このシーンも入れなきゃ、あれも言っておかなきゃってな感じで、エピソードがギュウギュウ詰め込まれ、ところどころ中途半端に投げ出されたまま、大わらわで展開していく。ついていくのが、しんどい。
言わんとしていることは哲学的で、何となくこういうことじゃないかと思っている。大昔、大学の一般教養の哲学で習ったヘーゲルの「弁証法的発展」。ちょっと知識があやふやだが、ある命題(A)があり、これを否定または矛盾するアンチテーゼ(B)が出てきて、それらが止揚されると、(A)も(B)も統合され、でも(A)でも(B)でもない、一段と高い段階の(C)へと発展するみたいな理論。つまり、理想郷ボルテックスは破壊も死も(=アンチテーゼ)を封じ込めてしまったので、新たな創造(=止揚)が生まれないのである。みんなが幸せそうだけど、過去の知識を食いつぶしているだけで、無気力な人間ばかりが増産され、衰退していくしかない世界。そこに獣人ゼットというアンチテーゼが入ってくる。逞しい肉体でセクシーオーラをギラギラと放って、ボルテックスの人間が失った生殖能力を復活させただけでなく、他の獣人たちをボルテックスに引き連れてきて殺戮させるなど破壊と死も導き入れる。その彼がボルテックスの全知識を受け継いだ時、ボルテックスと獣人という二元的世界は滅び、新しい世界へと止揚されることになる。それは、ゼットとボルテックスの指導者コンスエラが生殖の営みをして、新しい命をはぐくむという形で象徴されているように思う。
ジョーン・コネリー。若い頃はセックス・シンボルとして人気が高かった俳優だと思うが、そうした魅力をむんむん振りまいている。ショーン演じるゼッドは、最初は野蛮で無知な人間だ。ショーン・コネリーがアホっぽく見えて、何でこんな役を引き受けたのかなーと思っていた。ところが、後半、彼はどんどん賢くなっていく。その変わりよう。衣装は相変わらず赤褌一丁でも(笑)、表情に知性が宿り、新しい世界の創造者としての品をたたえていく。たたずまいや僅かな表情の違いとか、こんな繊細な演じ分けができる俳優って、そんなにいないよなぁと思う。
音楽はヴェートーベン。さて問題。「ソイレント・グリーン」といえば第6番、「時計じかけのオレンジ」といえば第9番、そして「ザルドス」といえば何番?。破壊と創造に、厳かさを漂わせるような音楽。

